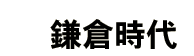- 前へ
- 次へ
鎌倉時代は,日本の国家形成という観点からみると,画期的な時代ということができます。ここで初めて貴族ではなく武士による封建的な支配体制がスタートしたからです。源氏は平氏と競合しながら,その力を蓄えていきましたが,東国の武士が,平氏の政権よりも強力な基盤をかためるには,その拠点は京都ではなく,鎌倉である必要がありました。そして鎌倉幕府は,源氏3代のあと,執権職の北条氏が承久の乱や元軍襲来などの戦乱のなかで公家政権をおさえ,全国を治めるようになりました。
一方,この激動の時代は新しい仏教を生み,貴族の文化を基礎にしながらも,雄壮な武士の文化をつくりだした時代でもありました。
武士による政治は,以後,江戸時代の終わりまで700年近くも続きました。
| 西暦 | 元号 | 日本のできごと(政治・経済・社会) | 西暦 |
|
西暦 |
|
|---|
| 1185 | 文治1 |  源頼朝が守護・地頭をおく。武家政治が始まり,鎌倉幕府が成立 源頼朝が守護・地頭をおく。武家政治が始まり,鎌倉幕府が成立 |
1185 | このころ西行『山家集』,『保元物語』『平治物語』 | 1185 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | 建久2 | 1191 | 栄西が臨済宗をつたえる | 1191 | ||
| 1192 | 3 | 源頼朝が征夷大将軍となる | 1192 | このころ新仏教(鎌倉仏教)が広まる | 1192 | |
| 1203 | 建仁3 | 源実朝が3代将軍となり,北条時政が執権となる | 1203 |  運慶・快慶「東大寺南大門金剛力士像」 運慶・快慶「東大寺南大門金剛力士像」 |
1203 | |
| 1205 | 元久2 | 1205 | 藤原定家ら『新古今和歌集』 | 1206 | チンギス=ハンがモンゴルを統一。モンゴル帝国を建てる | |
| 1212 | 9 | 1212 | 鴨長明『方丈記』 | 1212 | ||
| 1214 | 建保2 | 1214 | 源実朝『金槐和歌集』 | 1215 | 英 マグナ=カルタを定める | |
| 1219 | 承久1 |  源実朝,鶴岡八幡宮で暗殺される。源氏断絶する 源実朝,鶴岡八幡宮で暗殺される。源氏断絶する |
1219 | このころ『平家物語』 | 1219 | チンギス=ハンが西アジアに遠征する(~1224) |
| 1221 | 3 |  承久の乱おこる。乱後,京都に六波羅探題をおく 承久の乱おこる。乱後,京都に六波羅探題をおく |
1221 | 1221 | ||
| 1224 | 元仁1 | 1224 |  親鸞が浄土真宗を開く 親鸞が浄土真宗を開く |
1224 | ||
| 1227 | 安貞1 | 1227 |  道元が曹洞宗を伝える 道元が曹洞宗を伝える |
1227 | ||
| 1232 | 貞永1 | 北条泰時が御成敗式目(貞永式目)を定める | 1232 | 1232 | ||
| 1253 | 建長5 | 1253 |  日蓮が日蓮宗を開く 日蓮が日蓮宗を開く |
1260 |  モンゴル帝国でフビライが皇帝に即位する モンゴル帝国でフビライが皇帝に即位する |
|
| 1268 | 文永5 | フビライの国書をもって,高麗の使者が大宰府に来る | 1253 |  このころ北条実時,金沢文庫を設立する このころ北条実時,金沢文庫を設立する |
1268 | |
| 1274 | 11 | 文永の役(元・高麗軍が襲来する)-元寇 | 1274 |  一遍が時宗を開く 一遍が時宗を開く |
1271 | 中 モンゴルが国号を元とする |
| 1276 | 建治2 | 博多(福岡県)の沿岸に防塁を築く | 1276 | 1279 | 中 元が南宋をほろぼし,中国を統一する | |
| 1281 | 弘安4 | 弘安の役(元・高麗・江南軍がふたたび襲来)-元寇 | 1293 |  『蒙古襲来絵詞』 『蒙古襲来絵詞』 |
1281 | |
| 1297 | 永仁5 | 幕府が永仁の徳政令を出す | 1297 |  このころ『一遍上人絵伝』 このころ『一遍上人絵伝』 |
1299 |  伊 このころマルコ=ポーロ『東方見聞録(世界の記述)』 伊 このころマルコ=ポーロ『東方見聞録(世界の記述)』 |
印はインド,
中は中国,
朝は朝鮮,
英はイギリス,
伊はイタリア,
仏はフランス,
蘭はオランダ, 独はドイツ, 露はロシア, 米はアメリカ, ソはソ連, 西はスペイン, パはパキスタンのことです 。
蘭はオランダ, 独はドイツ, 露はロシア, 米はアメリカ, ソはソ連, 西はスペイン, パはパキスタンのことです 。